ロシア絵本的日常【ダイアリー】
11/12 マーヴリナ
2020年11月12日
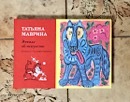
「タチヤーナ・マーヴリナ 芸術についての研究」を再入荷。鮮やかな色の表紙は半分は布張りになっている。1902年に生まれたマーヴリナは若い時期に前衛芸術の光と影を体験することになるが、以降古い都市を旅し、ロシア民芸の世界、農民芸術の探求を始め、多くの民話の挿絵を描き、1976年にはロシアで初めての国際アンデルセン賞を受賞する。
平成17年に国際子ども図書館で開催された松居直氏の講演会「ロシアの絵本を日本の子どもに」で松居氏はマーヴリナについて、本当にロシアそのものを表現したかった芸術家と表現。また、絶対にロシアを離れないという信条を持っていたけれど、ただ生涯に一度だけアンデルセン賞の授賞式のためにアテネにだけ行ったことがあるそうだ。
またこの本には風景画はもちろん、肖像画や静物画、そしてまたたくさんの裸婦像、などが収録されており、民話挿絵とはまた異なる側面からマーヴリナの芸術を堪能することができる。折々のポートレートも素敵だ。
マーヴリナが生涯をかけてそのほとばしる筆先で迫ろうとしたロシアの真髄。(直)