ロシア絵本的日常【ダイアリー】
2/12 ラリックとバレエ・リュス
2020年02月12日



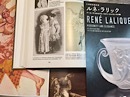
アール・ヌーヴォーの宝飾デザイナーであったラリックがなぜガラスを用いてアール・デコを代表する存在になったのか、については時代の変化が大きな要因であることは間違いはないのだが、また別の具体的な要素のひとつとしてバレエ・リュスの1910年の「火の鳥」公演を見て衝撃を受けたこと、をあげている商業記事を見つけた。https://precious.jp/articles/-/192
そして、そこからバレエ・リュスがなぜ「火の鳥」を上演したのかについての東大大学院人文社会系研究科準研究員(2019)である平野氏の研究文献「バレエ・リュス初期作品《火の鳥》研究 民話から生まれた「火の鳥」の妖艶な女性像」にたどり着き、拝読させていただいた。https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=28047&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1
これによると「火の鳥」上演は、当時ロシアで文学や美術の世界で大きなテーマであったロシア民話をバレエ・リュスでも取り上げるべきだとの考えに基づいて、初めて取り組んだロシア民話主題の題目だったとのこと。
衣装はレオン・バクストとゴロヴィン。手持ちの図録「魅惑のバレエコスチュームバレエ・リュス展」には、従者の衣装や大胆な衣装を身につけた小さいけれど当時の舞台の一コマの写真がある。音楽はストラヴィンスキー。何とか当時のラリックの衝撃に思いを馳せてみたいものだが…。それにしても主題的にロシアの魂的存在の民話に立ち返り作られたバレエが、新しい時代を切り開くアーティストに多大な影響を与えた、というのは興味深いことではある。
バレエ・リュスといえば、ビリービンもアンナ・パブロワの衣装デザインをしていたりするのだが、それらは「イヴァン・ヤコヴレヴィチ・ビリービン」で見られる。バレエは偉大だ。(直)