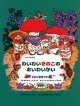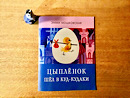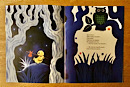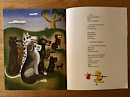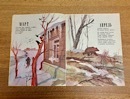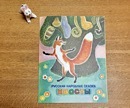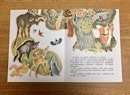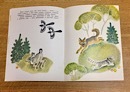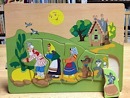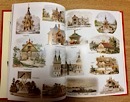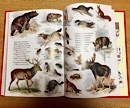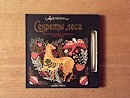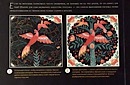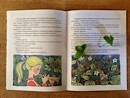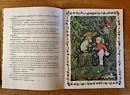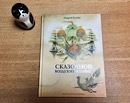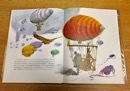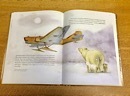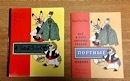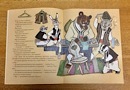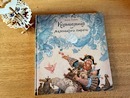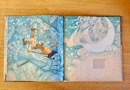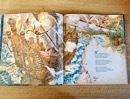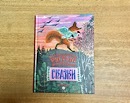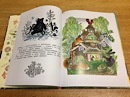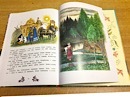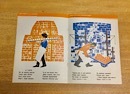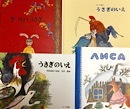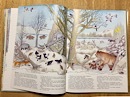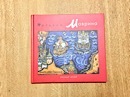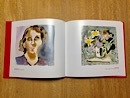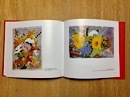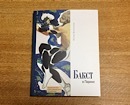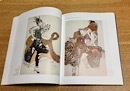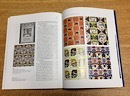美しいロシア絵本の世界を是非お手元でお楽しみください。
ロシア絵本的日常【ダイアリー】カテゴリ
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
出版書籍販売
|
|
商品カテゴリ一覧
作家名等一覧
- E.ラチョフ
- ヴァスネツォーフ
- ビリービン
- チュコフスキー
- ウスペンスキー
- チャルーシン親子
- マヤコフスキー
- T.マーヴリナ
- ブラートフ&ヴァシーリエフ
- Г・スピーリン
- アントン・ロマーエフ
- コナシェーヴィチ
- レーベデフ
- ボリス・デフテリョーフ
- ベヌア
- ナールブト
- トカチェンコ&ドゥーディン
- その他
- 民芸品作家・サーシャさん
- きのこ関連
- マイ・ミトゥーリチ
- レフ・ミーリチン
- ロジャンコフスキー
- ガルローフ
- スタラーステ
- アーノルド・ローベル
- リスべート・ツヴェルガー
- エリザベータ・ヴァスネツォーフ
- ステーエフ
- ヤールブソワ
- パヴリーシン
- ニコライ・ウスチーノフ
- トクマコフ
- トルストイ
- イーゴリ・オレイニコフ
- イリヤ・カバコフ
- ボリス・カラウシン
- ウスチノフ
- ナディア・コズリナ まきのはらようこ
- マリヤ・パブロワ
- 20-30年代復刻本関連
- エリセーエフ
- ヴィクトル・ヴァスネツオフ
- ご注文者様専用
- バスマノーヴァ
- アンナ・デスニツカヤ
- オストロフ
- レオン・バクスト
- ダーヴィト・ハイキン
- ヴィタリー・スタツィンスキー
- ザリツマン
- カラウーシン
- 児島宏子
- ローシン
- マカレンコ
- グーセフ
- ガリーナ・スカティナ
- ナタリヤ・コンドラトヴァ
- ナターリヤ・チャルーシン
- アレクセイ・チャルーシン
- キリル・オフチンニコフ
- アレクサンドル・ロシキン
- ミルコ・ハナーク(チェコ)
- ディック・ブルーナ(オランダ)
- ヴァレリー・ゴルバチョフ
- チジコフ
- 小我野明子
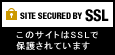
|
ホーム |
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
記事検索
ロシア絵本的日常【ダイアリー】:1982件
4/1 ハイキン
3/31 雪溶け
3/30 しっぽ
3/29 お知らせ
3/28 パズル
3/26 オオバコ
3/25 暗闇
3/24 イチゴの誘惑
3/23 空を飛ぶ
3/21 もりのようふくやさん
3/21 猫さん
3/19 海賊
3/18 夕暮れ
3/17 カップ
3/16 植物園へ
3/14 うさぎのいえ
3/13 3月
3/12 ロシア美術館
3/11 レオン・バクスト
3/10 サハリン
|
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス