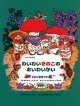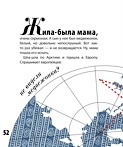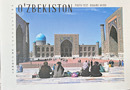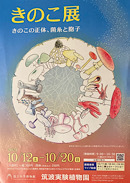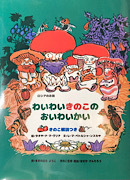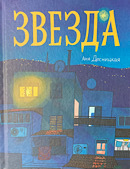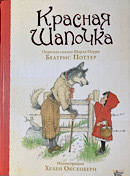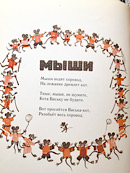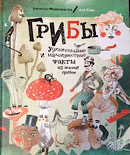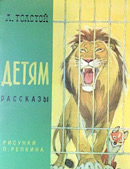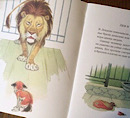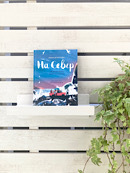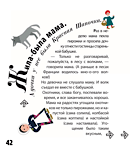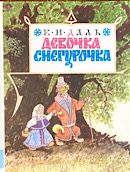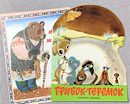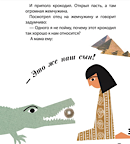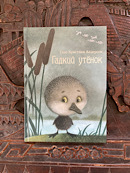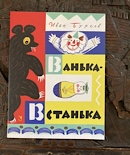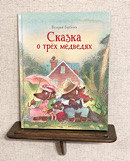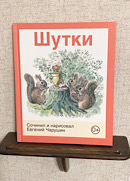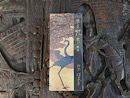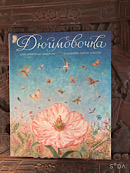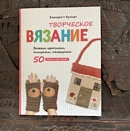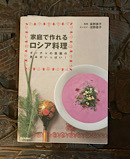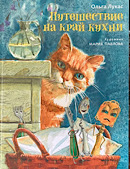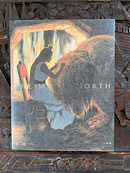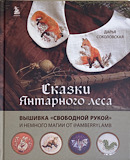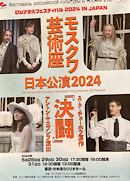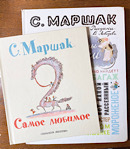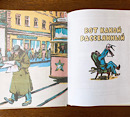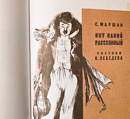美しいロシア絵本の世界を是非お手元でお楽しみください。
ロシア絵本的日常【ダイアリー】カテゴリ
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
出版書籍販売
|
|
商品カテゴリ一覧
作家名等一覧
- E.ラチョフ
- ヴァスネツォーフ
- ビリービン
- チュコフスキー
- ウスペンスキー
- チャルーシン親子
- マヤコフスキー
- T.マーヴリナ
- ブラートフ&ヴァシーリエフ
- Г・スピーリン
- アントン・ロマーエフ
- コナシェーヴィチ
- レーベデフ
- ボリス・デフテリョーフ
- ベヌア
- ナールブト
- トカチェンコ&ドゥーディン
- その他
- 民芸品作家・サーシャさん
- きのこ関連
- マイ・ミトゥーリチ
- レフ・ミーリチン
- ロジャンコフスキー
- ガルローフ
- スタラーステ
- アーノルド・ローベル
- リスべート・ツヴェルガー
- エリザベータ・ヴァスネツォーフ
- ステーエフ
- ヤールブソワ
- パヴリーシン
- ニコライ・ウスチーノフ
- トクマコフ
- トルストイ
- イーゴリ・オレイニコフ
- イリヤ・カバコフ
- ボリス・カラウシン
- ウスチノフ
- ナディア・コズリナ まきのはらようこ
- マリヤ・パブロワ
- 20-30年代復刻本関連
- エリセーエフ
- ヴィクトル・ヴァスネツオフ
- ご注文者様専用
- バスマノーヴァ
- アンナ・デスニツカヤ
- オストロフ
- レオン・バクスト
- ダーヴィト・ハイキン
- ヴィタリー・スタツィンスキー
- ザリツマン
- カラウーシン
- 児島宏子
- ローシン
- マカレンコ
- グーセフ
- ガリーナ・スカティナ
- ナタリヤ・コンドラトヴァ
- ナターリヤ・チャルーシン
- アレクセイ・チャルーシン
- キリル・オフチンニコフ
- アレクサンドル・ロシキン
- ミルコ・ハナーク(チェコ)
- ディック・ブルーナ(オランダ)
- ヴァレリー・ゴルバチョフ
- チジコフ
- 小我野明子
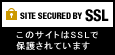
|
ホーム |
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
記事検索
ロシア絵本的日常【ダイアリー】:1977件
バーバ・ヤガー
10/27 かわいい
10/20 テレモーク
10/12 唐突に
10/5 驚くべき
9/28 曼珠沙華
9/14 カクトラノオ
9/7 頭巾
9/1 お話会
8/4 ブルーベリー
7/27 ベランダ
7/21 起き上がりこぼし
7/13 松島
7/6 バッタ
6/30 トヨタ
6/23 混然一体
6/15 半夏生
6/9 北欧
6/2 ニコライ堂
5/25 散漫
|
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス