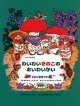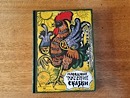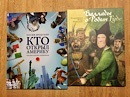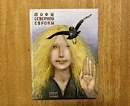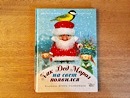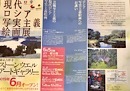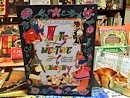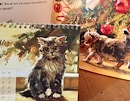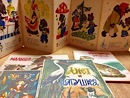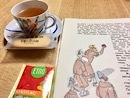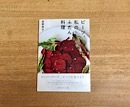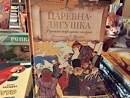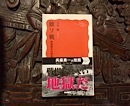美しいロシア絵本の世界を是非お手元でお楽しみください。
ロシア絵本的日常【ダイアリー】カテゴリ
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
出版書籍販売
|
|
商品カテゴリ一覧
作家名等一覧
- E.ラチョフ
- ヴァスネツォーフ
- ビリービン
- チュコフスキー
- ウスペンスキー
- チャルーシン親子
- マヤコフスキー
- T.マーヴリナ
- ブラートフ&ヴァシーリエフ
- Г・スピーリン
- アントン・ロマーエフ
- コナシェーヴィチ
- レーベデフ
- ボリス・デフテリョーフ
- ベヌア
- ナールブト
- トカチェンコ&ドゥーディン
- その他
- 民芸品作家・サーシャさん
- きのこ関連
- マイ・ミトゥーリチ
- レフ・ミーリチン
- ロジャンコフスキー
- ガルローフ
- スタラーステ
- アーノルド・ローベル
- リスべート・ツヴェルガー
- エリザベータ・ヴァスネツォーフ
- ステーエフ
- ヤールブソワ
- パヴリーシン
- ニコライ・ウスチーノフ
- トクマコフ
- トルストイ
- イーゴリ・オレイニコフ
- イリヤ・カバコフ
- ボリス・カラウシン
- ウスチノフ
- ナディア・コズリナ まきのはらようこ
- マリヤ・パブロワ
- 20-30年代復刻本関連
- エリセーエフ
- ヴィクトル・ヴァスネツオフ
- ご注文者様専用
- バスマノーヴァ
- アンナ・デスニツカヤ
- オストロフ
- レオン・バクスト
- ダーヴィト・ハイキン
- ヴィタリー・スタツィンスキー
- ザリツマン
- カラウーシン
- 児島宏子
- ローシン
- マカレンコ
- グーセフ
- ガリーナ・スカティナ
- ナタリヤ・コンドラトヴァ
- ナターリヤ・チャルーシン
- アレクセイ・チャルーシン
- キリル・オフチンニコフ
- アレクサンドル・ロシキン
- ミルコ・ハナーク(チェコ)
- ディック・ブルーナ(オランダ)
- ヴァレリー・ゴルバチョフ
- チジコフ
- 小我野明子
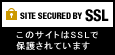
|
ホーム |
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
記事検索
ロシア絵本的日常【ダイアリー】:1982件
11/11 カレンダー
11/10 アートと絵本
11/10 祝・70周年
11/8 雄鶏
11/7 マフラー
11/6 おやつ
11/5 肝臓
11/4 西荻散歩
11/3 個人美術館
11/2 次回は
11/1 秋日和
10/31 こねこ
10/30 ジャバラ
10/29 連結
10/28 ビーツ!
10/27 ブックフェスティバル
10/26 忘却と記憶
10/25 ゲンロンカフェ
10/24.ビリービン
10/23 独ソ戦
|
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス