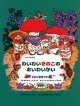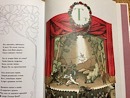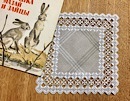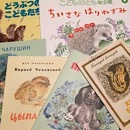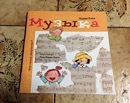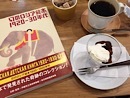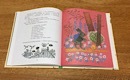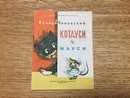美しいロシア絵本の世界を是非お手元でお楽しみください。
ロシア絵本的日常【ダイアリー】カテゴリ
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
出版書籍販売
|
|
商品カテゴリ一覧
作家名等一覧
- E.ラチョフ
- ヴァスネツォーフ
- ビリービン
- チュコフスキー
- ウスペンスキー
- チャルーシン親子
- マヤコフスキー
- T.マーヴリナ
- ブラートフ&ヴァシーリエフ
- Г・スピーリン
- アントン・ロマーエフ
- コナシェーヴィチ
- レーベデフ
- ボリス・デフテリョーフ
- ベヌア
- ナールブト
- トカチェンコ&ドゥーディン
- その他
- 民芸品作家・サーシャさん
- きのこ関連
- マイ・ミトゥーリチ
- レフ・ミーリチン
- ロジャンコフスキー
- ガルローフ
- スタラーステ
- アーノルド・ローベル
- リスべート・ツヴェルガー
- エリザベータ・ヴァスネツォーフ
- ステーエフ
- ヤールブソワ
- パヴリーシン
- ニコライ・ウスチーノフ
- トクマコフ
- トルストイ
- イーゴリ・オレイニコフ
- イリヤ・カバコフ
- ボリス・カラウシン
- ウスチノフ
- ナディア・コズリナ まきのはらようこ
- マリヤ・パブロワ
- 20-30年代復刻本関連
- エリセーエフ
- ヴィクトル・ヴァスネツオフ
- ご注文者様専用
- バスマノーヴァ
- アンナ・デスニツカヤ
- オストロフ
- レオン・バクスト
- ダーヴィト・ハイキン
- ヴィタリー・スタツィンスキー
- ザリツマン
- カラウーシン
- 児島宏子
- ローシン
- マカレンコ
- グーセフ
- ガリーナ・スカティナ
- ナタリヤ・コンドラトヴァ
- ナターリヤ・チャルーシン
- アレクセイ・チャルーシン
- キリル・オフチンニコフ
- アレクサンドル・ロシキン
- ミルコ・ハナーク(チェコ)
- ディック・ブルーナ(オランダ)
- ヴァレリー・ゴルバチョフ
- チジコフ
- 小我野明子
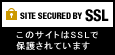
|
ホーム |
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
記事検索
ロシア絵本的日常【ダイアリー】:1979件
3/12 バス旅
3/11 黒猫
3/10 なんと嬉しい
3/9 劇場
3/8 ドイリー
3/7 新潟ロシア村
3/6 繋がり
3/5 三代目。
3/4 3月8日のこと
3/3 春3月
3/2 ゆっくり
3/1 お人形
2/28 音楽の絵本
2/27 日々の西荻
2/26 おてんば娘
2/25 オリンピック
2/24 ロシヤ語辞典
2/23 ぬすまれたのは
2/22 今日は
2/21 エストニアの絵本
|
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス