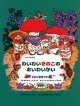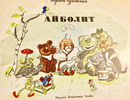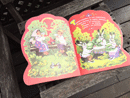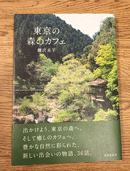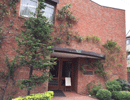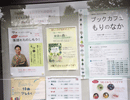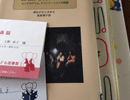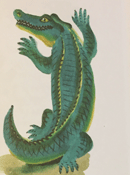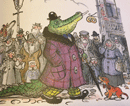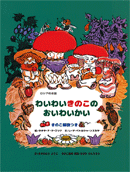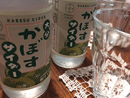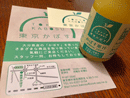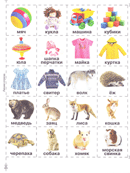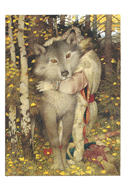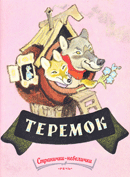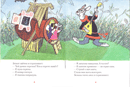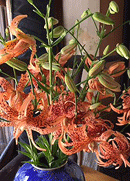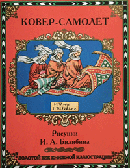美しいロシア絵本の世界を是非お手元でお楽しみください。
ロシア絵本的日常【ダイアリー】カテゴリ
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
出版書籍販売はこちら(最新順)
|
|
商品カテゴリ一覧
作家名等一覧
- E.ラチョフ
- ヴァスネツォーフ
- ビリービン
- チュコフスキー
- ウスペンスキー
- チャルーシン親子
- マヤコフスキー
- T.マーヴリナ
- ブラートフ&ヴァシーリエフ
- Г・スピーリン
- アントン・ロマーエフ
- コナシェーヴィチ
- レーベデフ
- ボリス・デフテリョーフ
- ベヌア
- ナールブト
- トカチェンコ&ドゥーディン
- その他
- 民芸品作家・サーシャさん
- きのこ関連
- マイ・ミトゥーリチ
- レフ・ミーリチン
- ロジャンコフスキー
- ガルローフ
- スタラーステ
- アーノルド・ローベル
- リスべート・ツヴェルガー
- エリザベータ・ヴァスネツォーフ
- ステーエフ
- ヤールブソワ
- パヴリーシン
- ニコライ・ウスチーノフ
- トクマコフ
- トルストイ
- イーゴリ・オレイニコフ
- イリヤ・カバコフ
- ボリス・カラウシン
- ウスチノフ
- ナディア・コズリナ まきのはらようこ
- マリヤ・パブロワ
- 20-30年代復刻本関連
- エリセーエフ
- ヴィクトル・ヴァスネツオフ
- ご注文者様専用
- バスマノーヴァ
- アンナ・デスニツカヤ
- オストロフ
- レオン・バクスト
- ダーヴィト・ハイキン
- ヴィタリー・スタツィンスキー
- ザリツマン
- カラウーシン
- 児島宏子
- ローシン
- マカレンコ
- グーセフ
- ガリーナ・スカティナ
- ナタリヤ・コンドラトヴァ
- ナターリヤ・チャルーシン
- アレクセイ・チャルーシン
- キリル・オフチンニコフ
- アレクサンドル・ロシキン
- ミルコ・ハナーク(チェコ)
- ディック・ブルーナ(オランダ)
- ヴァレリー・ゴルバチョフ
- チジコフ
- 小我野明子
- 上野直子
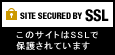
|
ホーム |
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
ロシア絵本的日常【ダイアリー】
記事検索
ロシア絵本的日常【ダイアリー】:1990件
8/8 アイボリット先生。
8/7 ぴょん吉。
8/6 森。
8/5 夏の課題図書。
8/4 なぞなぞ。
8/3 知らなかったこと(ヨウシュヤマゴボウ)
8/2 わに。
8/1 国立科学博物館「きのこ展」2017
7/31 西荻窪「森のこと」さん。
7/30 東京かぼすさん。
7/29 起き上がりこぼし。
7/28 ブルーベリー。
7/27 初めての言葉。
7/26 まなざし。
7/25 耳が特徴。
7/24 ハンディ。
7/23 夏の色。
7/22 積乱雲。
7/21 にぎやか。
7/20 空を飛ぶ。
|
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス